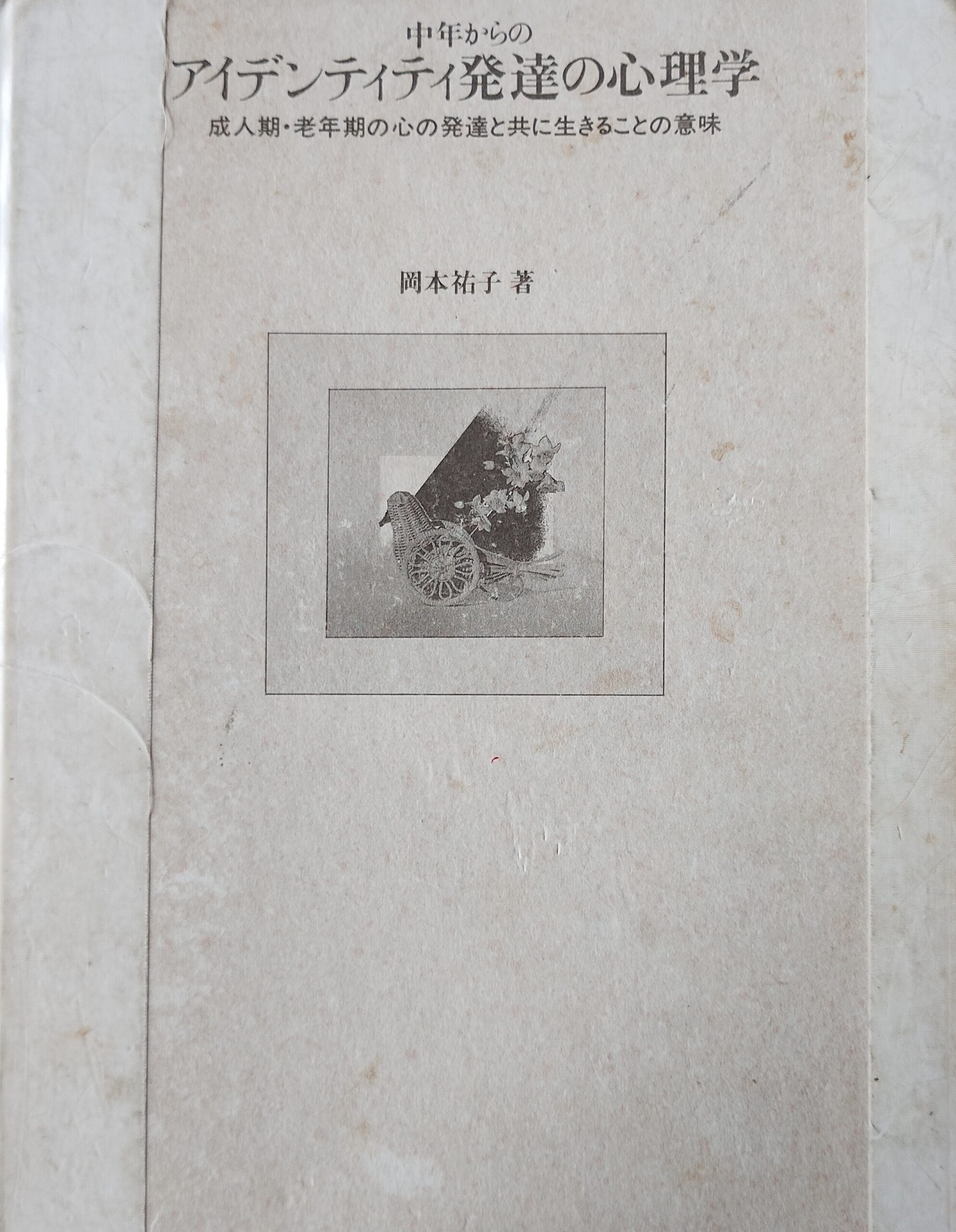アイデンティティとは、「自分とは何者か」、「本当の、正真正銘の自分とは何か」ということを意味する
フリーランスの翻訳者として、10年働いた。仕事は面白かったけれど、自宅やカフェでパソコンに向かう毎日は孤独すぎた。もう一度外で、人の中で働きたいという思いが日に日に募り、50を目の前にして飛び出した。10年ぶりに、「就職」したのだ。
翻訳者になる前は、企業でふつうに働いていた。外資系でバリバリやっていた時期もある。(なんとかなるだろう)とのん気に構えていたけれど、現実は甘くなかった。事務の仕事がこんなにも複雑で、覚えることが多く、機転や気配りを要求されるものだったとは(!) 同僚とデスクを並べて働く環境も、10年ひとりで仕事をしていた私は慣れるのに苦労した。
アラフィフでの転職失敗は、痛すぎた。
これからどうしようーーその職場を3カ月で辞めて以来、ずっとそればかり考えてきた。いっそ何かまったく新しいことを始めようか。それとももうガツガツ働くのはやめて、パートにでも出ようか。ぐるぐるぐるぐる悩み続けて、この本にたどり着いた。読んでよかった。
*
よかったのは、ぐるぐるぐるぐる悩んでいるのは私だけではないと再認識できたこと。
外面的にはみんな、社会的役割と責任を果たし、安定した大人の人生を生きているように見える。しかし、その心の内面では、必ずしもアイデンティティ達成とはいえない人々も数多く存在している
仕事がいかに「アイデンティティ」の安定に重要か分かったこと。
有職者の86%が、「職業を通して自己確立感・安定感を得たと報告しており、職業はアイデンティティの安定した基盤となり得ているようであった。また、彼女たちは全員、仕事の他に趣味をもつとか、ゆとりを持って仕事をしたいなど、仕事を続ける範囲内で、再方向づけを行っていた(杉村、1993)
そして、人生の各ステージで直面する課題から逃げず、クリアしていくことが大事だということ。
A型(定年積極的歓迎型)の人々は、仕事に対して積極的にとりくみ生きがいを感じており、また勤勉性や有能感も高い。(中略)長い肯定的な将来願望をもち、はっきりとした自分の役割を自覚して主体的に取り組んでおり、また家族や友人とも親密な関係を維持しているなど、各ステージの課題をうまく達成している。(中略)このような研究から見ると、定年退職危機を解決し、退職にともなうストレスをうまく解消するためには、それ以前のライフステージにおける心理・社会的課題の達成が重要な要因であることがわかる
*
やっぱり、「仕事」は大事なのだ。自分の仕事が誰かの役に立っていると実感できること。そのことに誇りを持てること。それが自己肯定につながり、他の誰とも違う自分の「アイデンティティ」になっていく。
そして、残したままの人生の課題があるなら、その課題に自分なりの答えを出さないといけない。でないといつまでも、「本当の自分(アイデンティティ)」探しが続くーー。
派遣の契約が年度末で切れる。今の仕事をもう1年続けることも、たぶんできる。もう一度、じっくり考えてみよう。仕事を変えるにしても、変えないにしても。
アイデンティティ達成のレベルは、まず、アイデンティティの危機をいかに深く気づき、体験し、そしていかにしっかりと主体的に再体制化できたかで、とらえることができる
しっかりと主体的に、これからの生き方に納得がいく答えを出したい。この壁を越えて、また新しい景色を見るのを楽しみに。
| 書名 | 中年からのアイデンティティ発達の心理学: 成人期・老年期の心の発達と共に生きることの意味 |
| 著者 | 岡本 祐子 |
| 出版社 | ナカニシヤ出版 |
| 出版年月 | 1997年6月 |
| ページ数 | 231ページ |
著者について(Wikipediaより抜粋):
日本の臨床心理学者、発達心理学者、広島大学名誉教授、教育学博士。エリク・エリクソンの理論を基盤としたライフサイクルの心理力動的研究、成人期のアイデンティティ研究に関する業績で知られる。