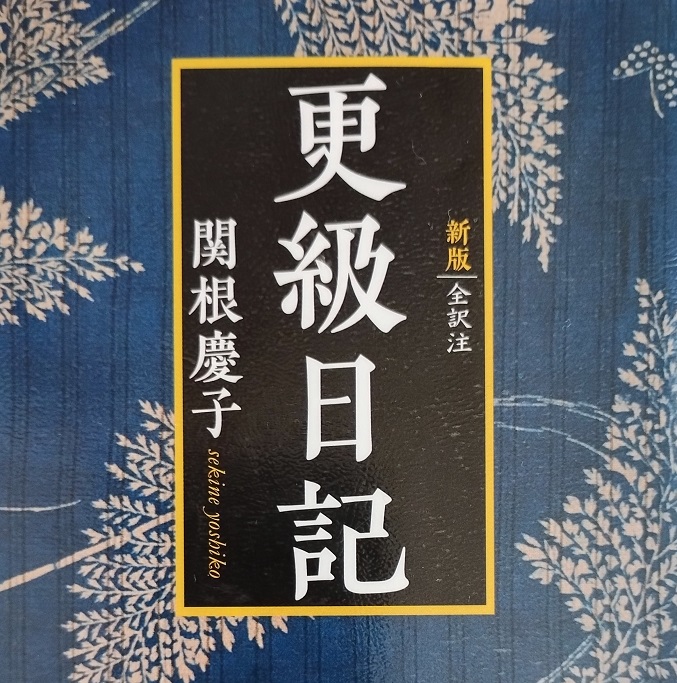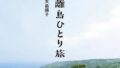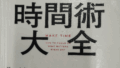昔々、千年前の平安時代、菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)という中流貴族の女性が書いた、自身の半生記。
「作者が51歳ぐらいのときに、これまでの人生をふりかえって書いた本」で、「50を過ぎて人生に一抹の後悔、無念」を感じていたらしいとどこかで知って、読んでみたくなった。私も今まさに51歳、これまでの人生をふりかえれば、大なり小なり後悔もある。読んでみて感じたのは、千年経っても「人間は変わらないな」ということ。14歳のころ作者は、
われはこのごろわろきぞかし、さかりにならば、かたちも限りなくよく、かみもいみじく長くなりなむ。光の源氏の夕顔、宇治の大将の浮舟の女ぎみのやうにこそあらめ
(私は今器量もよくないことだ。年ごろになったら、顔かたちもこの上なくよく、髪も非常に長くなるだろう。光源氏の愛した夕顔や、宇治の大将の愛した浮舟の女君のようにきっとなっているだろう)
なんて淡い期待を抱いていた。「自分もいつかSNSのインフルエンサーみたいな美人になる(なりたい)」と毎日鏡を眺めているうちの次女(14歳)みたいだ。そして18歳ぐらいになると、
いみじくやむごとなく、かたちありさま物語にある光源氏などのやうにおはせむ人を、年に一たびにても通はし奉りて、浮舟の女君のやうに、山里に隠し据ゑられて、花・紅葉・月・雪を眺めて、いと心細けにて、めでたからむ御文などを、時々まち見などこそせめ
(非常に身分が高くて容貌風采も物語に出てくる光源氏などのようでいらっしゃる人を、年に一度でもいいから通わせ申して、浮舟の女君のように山里にひっそり住まわされていて、花・紅葉・月・雪などをながめて、たいそう心細いようなようすで、結構なようなお手紙などを、ときどき待って見などしたいものだ)
なんて妄想をしている。ドラマやアニメを見て、ハイスペックのイケメンと素敵な恋をしてみたいと盛り上がっているうちの次女とまったく同じ。でも、変わらないのは少女時代だけじゃない。40代に入るとその心境は、
さしあたりてなげかしなどおぼゆる事などもないままに、ただ幼き人々を、いつしか思ふさまにしたてて見むと思ふに、年月の過ぎ行くを心もとなく、頼む人だに人のやうなるよろこびしてはとのみ思ひわたる心地たのもしかし
(現在さしあたって嘆かわしいなどと感じることもないので、ただ幼い子供たちを、早く思うように立派に成長させて見ようと思っていると、年月が過ぎていくのをまだるっこく感じ、今は頼む夫だけでも人なみに任官してくれたらとばかり思い続けている気持はなかなかたのもしかった)
安定した暮らしの中で、子どもの成長と夫の出世だけがもっぱらの関心事だなんて、どこかのだれかみたいじゃないか(笑)
作者は独身時代に仕事(宮仕え)も経験しているが、1年ほどで寿退社。その後はたまのパート勤務(姪の付き添いで出仕)をしたぐらいで、これといったキャリアもない。友人とのおしゃべりに花を咲かせたり、家庭からの解放感を味わったり、外に出るのはそれなりに楽しかった。でも、
宮づかへとても、もとは一すぢに仕うまつりつかばやいかがあらむ。時々たちいでば、何なるべくもなかめり
(宮仕えにしたところで、もともとそれ一途にお仕えし馴れたならどうだっただろうか、ときどき出仕するのだったら、何になろうはずもないようだ)
頑張って続けていれば、もう少し何者かになれたのでは、と一抹の後悔。「ひとつの仕事を一途に続けていれば」と悔やまれる気持ち、「何も成していない」という焦りのような気持ちーー。
わかる。私も出産後、育児との両立に悩み、キャリアを積んでいた会社を辞めてしまった。その後、翻訳者として独立したけれど、孤独な在宅ワークを10年続けたら人恋しくなって辞めてしまった。そんなこんなで、この部分に妙に共感。そして作者は50を過ぎて、夫に先立たれる。
いまは世にあらじ物とや思ふらむあはれ泣く泣く猶こそはふれ(中略)人々はみな、外に住みあかれて、故郷に一人、いみじう心ぼそく悲しくて、眺めあかしわびて…
(今はもう私のことも、この世にないもののように思っていらっしゃるのでしょうか。みじめに泣く泣く、それでもやっぱり生きてはおりますのよ。(中略)人々はみな、ほかの所に住みわかれて、私は元の家に一人で、たいそう心細く哀しくて、夜もぼんやりと物を思い明かしかねて…)
後悔、孤独、依存。物語ばかりにうつつを抜かしていないで、もっと仕事や精進に励めばよかった。夫とは死に別れ、子どもは家を出て行った。誰もいない、寂しい。もはや心のよりどころは仏様だけーー「自分はこうなりたくない」とすごく思ってしまった。
家族と暮らしていたときは家族の存在に頼り、家族なきあとは仏に頼る。いつも誰か、何かに頼らずにいられない作者。でも、夫が病に伏して10日後に突然亡くなってしまったら? 私も作者と同じになるんじゃないか? 大丈夫なんて言える自信はまったくない。私だって、夫と子どもの存在に大きく依存している自覚がある。
平安時代に中流貴族の娘・母・妻であった女性と、令和の現代を生きる中産階級の自分。私たちの違いは何だろう??
時代の影響を受け、時代の中に「ただよふ(漂う)」人の生。自分は生きている間に少しでも人として成長し、少しでも何か良いものを次の時代に渡せるだろうか? 古典にふれて、そんなことまで真面目に考えてしまった。
| 書名 | 新版 更級日記 全訳注 |
| 著者 | 関根 慶子 |
| 出版社 | 講談社学術文庫 |
| 出版年月 | 2015年12月 |
| ページ数 | 384ページ |